Cross Talk機電・情報系社員座談会

ここでは、グループ各社から集まった機械・電気・情報系専攻出身の若手社員たちに、学生時代の経験や入社のきっかけ、現在の仕事とそのやりがいについて語り合ってもらいました。若手社員が感じるHORIBAで働く「リアル」をお届けします。
Member
-

伊達
堀場製作所
設計開発(情報)
理工学研究科 人間システム工学専攻自動車メーカーの試験設備向けに、データマネジメントシステムの開発・設計を担当。
-

田中
堀場エステック
設計開発(機械)
自然科学研究科 機械科学専攻新型マスフローコントローラーの開発・評価業務に加え、既存製品の改善業務を担当。
-

沖野
堀場アドバンスドテクノ
設計開発(電気)
ソーシャルデザイン工学科既存製品の生産維持や、製品の部品変更に伴う基板の回路設計、評価業務を担当。
-

三木
堀場テクノサービス
設計開発(電気・情報)
工学部 電気システム工学科エンジニアが使用する治具や堀場テクノサービス独自の製品開発、ソフトウェア開発を担当。
※所属および記事内容は、取材当時のものです。
HORIBAに入社を決めた理由は
何でしょうか?
-

伊達 私は情報系の知識を活かしつつ、計測によって新たな価値を生み出せる環境に惹かれて入社を決めました。学生時代の研究はデータの収集と解析が中心で、目に見えないものが「はかる」ことで数値化・可視化されることに面白さを感じていました。就職活動で計測技術に特化したメーカーを探す中で、高度な「はかる」技術を持つ堀場製作所を見つけたんです。

-

田中 私も計測技術に特化したメーカーを志望していたことがきっかけです。私の研究は人間工学がテーマで、重心移動や筋電位の計測が欠かせず、計測技術の奥深さを実感していました。それでHORIBAに興味を持って調べるうちに、堀場エステックのマスフローコントローラーが半導体製造の要であると知って、計測技術で世界に貢献できると思い志望しました。また、会社説明会に登壇していた先輩社員のお話から、若くしてチャレンジできる環境が整っていると感じたのも理由の一つです。

-

沖野 私もHORIBAの会社説明会に参加したとき、堀場アドバンスドテクノが環境に関する事業に力を入れていることや働きやすい雰囲気であることを知って、この会社で働きたいと思いました。私は中学生のころから理系科目が好きで、電気分野に特化した勉強ができる高専に進学しました。環境問題に関心があり、地球環境を良くしたいというおもいと、高専で学んだ知識を活かして働けると思ったのが入社の理由です。
-

三木 私は大学で、燃料電池と太陽光発電を組み合わせた効率的な運用システムを研究していました。就職活動を始めたとき、研究室の先生に「お客様とコミュニケーションを取りながら働きたい」と相談したところ、「堀場テクノサービスを受けてみたら」とアドバイスされたんです。説明会に参加した際、会社についてあまり知らないことを正直に話すと、私一人のために丁寧に説明してくれました。その方の温かい対応から人を大事にしている会社だと感じたのと、私の学んできたことを活かしてお客様と近い距離で仕事ができる点に魅力を感じ、入社を決めました。
現在の仕事について教えて
ください。
-

伊達 私は今、堀場製作所の開発部門で、自動車業界向けのデータマネジメントシステムの開発・設計に携わっています。試験結果や試験設備の電力・ガス使用状況などのデータを集めて可視化することで、お客様の作業効率向上に貢献するシステムを開発することがミッションです。お客様ごとに知りたいデータが違うため、それに合わせた「一点もの」の開発ができるのはHORIBAの開発の面白さだと思います。
-

沖野 わかります。難しい要望でも、社内の力を合わせてどうにか応えられた時はとてもやりがいを感じます。
-

伊達 グループのどの会社にもそんな瞬間ってありますよね。それに加えて、お客様へのヒアリングからシステム設計、プログラミングを用いた開発、納品後の現地対応まで、ものづくりの一連の流れを担当できるのも大きなやりがいです。

-

田中 私は堀場エステックで機械設計者として、サプライヤーから部品の仕様や材質の変更申請があったときに、その調査や評価を行っています。主力製品であるマスフローコントローラーの安定供給を支え、会社の売上にも直結する重要な役割のため、非常にやりがいがあります。
-

沖野 私は堀場アドバンスドテクノで、製品の部品が生産中止になった際の代替部品選定と回路設計を担当しています。ただ図面に起こして設計するだけでなく、実際に手を動かして、試作や実機での動作確認を行い、設計した基板が意図どおり動くかどうかの電気評価まで行っています。幅広い知識が求められるので、自分のスキルアップにもつながっています。
-

三木 私は堀場テクノサービスで、お客様のところにある分析装置の状態をクラウドで集約して可視化するモニタリングシステムや、離れた場所にある分析装置をコントロールできるようにする遠隔操作のシステムを構築しています。
学生時代の経験が活きていると感じることはありますか?
-

田中 機械工学を専攻していたので、学生時代は四力(材料力学、熱力学、流体力学、機械力学)を中心に勉強していました。評価品に不具合が発生した際に原因を究明したり、評価結果の妥当性を検討したりなど、理論的なアプローチが必要な場面で四力の考え方は不可欠なため、毎日のように活用しています。
-

沖野 私も現在の電気設計の仕事に関係する、電気電子回路の基礎を幅広く学んでいました。既存回路を読み解いたり、業務で必要な知識を勉強したりすると、学生時代にやったなぁと思うことが多いのと同時にもっとちゃんと勉強しておけばよかったと後悔することもあります(笑)。また、高専では実習も多くあり、はんだ付けや結線をして動かす経験は現在の基板評価業務に活きていると感じます。
-

三木 私もメインの専攻は電気ですが、大学では電子、電磁波、通信、情報、プログラミングなど幅広く学んできました。HORIBAのものづくりは電気だけでなく、ソフトウェアや機械、化学、物理などさまざまな技術が組み合わさってできています。私自身は、学生時代の知識が今の仕事に直接結びついているとは言えませんが、仕事を通じて自分の専門分野をさらに強化できるだけでなく、その他の技術も学べる環境だと思っています。
-

伊達 専門領域にとらわれず幅広いキャリアを築けるところがHORIBAの特徴ですよね。ありがたいことに、私は大学で学んだプログラミングやネットワーク、データベースに関する知識を活かせています。具体的には、C#やAngularを使ったフロントエンドとバックエンドのシステム開発に加え、サーバやネットワークの構築、SQLを用いたデータベース設計など多岐にわたる業務に携わっています。学生時代に習得した理論的な知識が開発やインフラ設計に役立つ場面も多く、基礎を学ぶことの重要性を実感しています。
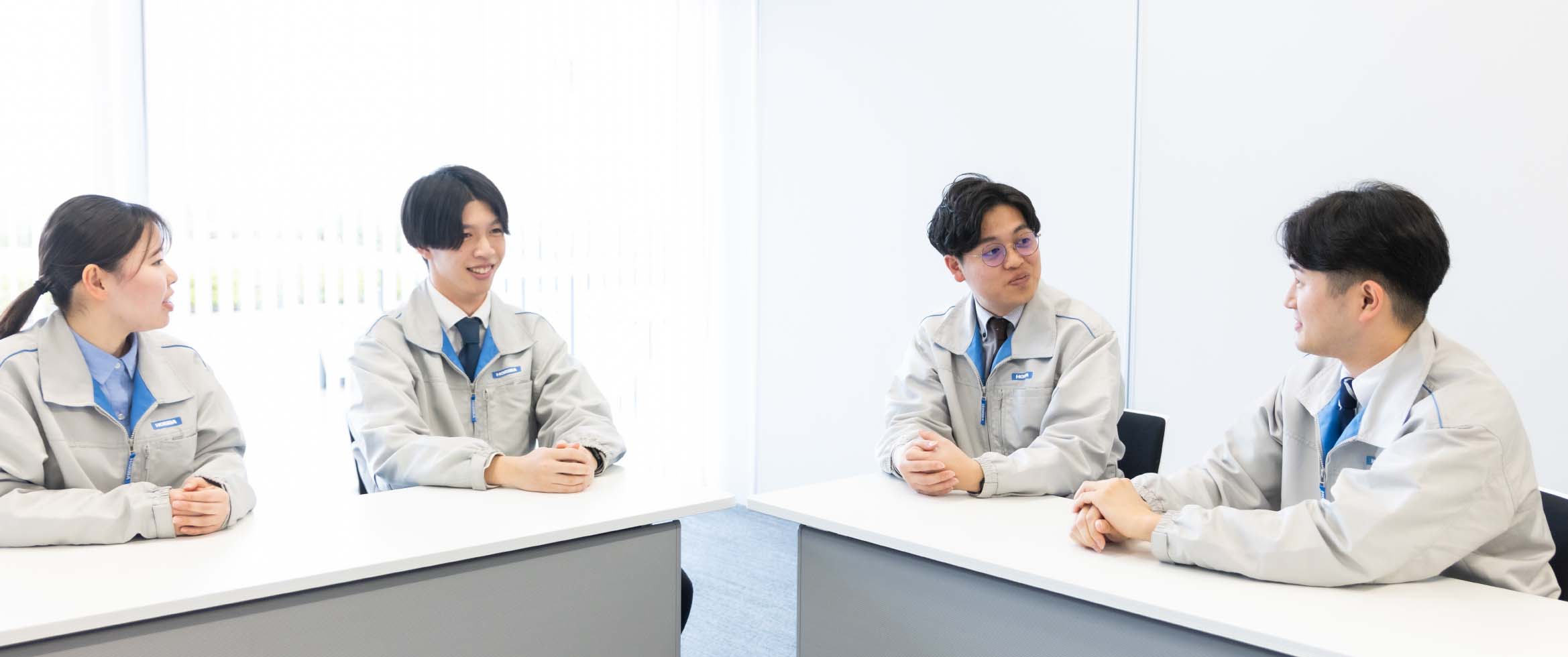
皆さんが思うHORIBAで働く魅力は
何でしょうか?
-

三木 失敗しても、それが前向きなチャレンジの結果であれば、怒られたりしないことだと思います。自分がミスをしたときも、「どう解決しようか?」と上司や先輩たちがみんな前向きにアドバイスをくれました。チャレンジを後押ししてくれる文化が根付いていると感じます。
-

田中 同感です。私の部署でも、仕事で思ったような成果が出なかったとしても「もう一度やってみよう」と先輩たちが背中を押してくれます。今までやったことのない分野にチャレンジしてみたくなり「経験がないんですが、やってもいいですか?」と上司に聞くと、「ぜひチャレンジしてみて」と後押ししてもらいました。その後も必要な知識のインプットやフォローを受けながら、無事に完遂することができました。

-

伊達 その文化はHORIBAグループ全体に共通していますね。「とりあえずやってみよう、責任は私が取るよ」と言ってくれるすてきな上司がたくさんいます。上下関係というより仲間意識が強いフラットな環境で、みんなで仕事をしている感じが働きやすさにつながっているんだと思います。
-

沖野 チャレンジの機会がたくさんあるのもHORIBAのいいところだと感じています。先ほどの話にもありましたが、ものづくりの始まりから終わりまで携わることができるので、自分の専門分野だけでなく、エンジニアとして幅広いキャリアを積むことができると思います。
-

田中 たしかに携わる範囲が広いので、難しいことも多いですが、周囲からの協力を得ながらエンジニアとしての成長を感じられています。
-

伊達 グローバルな環境も魅力ですよね。私の隣にはイギリス出身の同僚がいて、海外グループ会社の人々とも関わる機会が日常的にあります。
-

沖野 私のまわりにも、海外公募派遣制度を活用した方がいて、若くして海外にチャレンジできるのは非常に魅力的だと思います。
-

伊達 出張や出向だけでなく、そういった制度も活用して海外にチャレンジきるのはいいですよね。最近は、グループ各社をまたぐ事業の取り組みも増えていて、グループ間の連携を強化することで、これからさらに新しい価値が生まれていきそうです。私自身、自動車分野で培ったデータマネジメントソリューションを他の領域に展開するプロジェクトに関わっています。実は三木さんもそのプロジェクトメンバーで、オンライン会議では何度も同席していましたが、今日初めて実際にお会いできました(笑)。
-

三木 私も伊達さんにお会いできて嬉しいです。グループ間でコラボすると、視野が広がりますし、新しいチャレンジができると感じます。普段は違う場所で働いていても、グループ全体で重なる事業領域も多いので、積極的に関わっていきたいですね。
仕事のやりがいや今後の目標について教えてください。
-

沖野 私は仕事を通じて地球環境に貢献できていることが嬉しいです。私たちが扱う装置は水質や工場の排水を測るものなので、環境問題の解決に直接つながっています。会社全体でも梱包材の削減やSDGsなどの活動に力を入れているのが誇らしく、学生時代に思い描いていた夢が、今の仕事で実現できている実感があります。
-

伊達 私の仕事にもそれは言えますね。排ガスやバッテリーの計測技術を通じて、これからの環境に優しいモビリティ社会の実現に貢献できるのがやりがいです。エンジンもバッテリーも、高性能で環境に優しい製品を作るためには必ず「はかる」技術が必要になるので、これからますますHORIBAの強みが活きるはずです。しかも環境問題はグローバルな課題なので、アジアやアフリカなど、これから大きく経済成長を遂げる国や地域でも私たちの技術が貢献できると信じています。

-

田中 半導体の分野でも、HORIBAの存在感はますます強まっていると感じています。AIの進歩で高性能な半導体の需要が急激に伸びつづけている中で、当社のマスフローコントローラーもその製造に欠かせないものとなっています。半導体業界は技術革新が激しいですが、その製造に必要な薬品などを測定する技術は必要とされ続けます。競合他社との競争も厳しいですが、だからこそやりがいがあると感じています。
-

三木 プロとして成長できることが、私の感じるHORIBAの一番の魅力です。私が専門とするソフトウェアの世界ではAIが誰でも使える時代となり、AIに指示を出してプログラムを作ることが急速に広まっていますが、それでも最終的には“人”が責任を持ってコントロールする必要があります。特に私たちの仕事は、多種多様な製品の動作原理を理解しなければソフトウェアを作れないため、化学や流体力学の基礎的な知識も必要です。しかし、私たちの職場には、プロフェッショナルな先輩がたくさんいて、その方々の仕事から直接学ぶことができます。そんな先輩方のように、将来的には計測に関することなら何でも対応できるプロをめざしていきたいと思っています。
-

伊達 サイエンスの幅広い知識が求められるからこそ、仕事が面白いと私も感じています。いま科学の世界はどんどん専門化が進んでいますが、HORIBAで働く人の多くは、物理や化学、材料工学、機械工学、電気電子などさまざまな知識を組み合わせて、最高の製品を生み出そうとしています。幅広く科学に興味があり、ものづくりで社会に貢献したいという熱いおもいがある人には、本当にぴったりの会社です。HORIBAは自分の意見をしっかり持って、「これがやりたい」と言えば、基本的に快く受け入れてくれる会社です。向上心と行動力があれば、必ず成長できます。「チャレンジしたい」という気持ちがある人に、ぜひ入社してほしいと思います。



