Project Story #01カーボンニュートラル社会の実現へ
次世代の排ガス計測技術で
未来を切り開く

Prologue
近年、地球温暖化や気候変動の解決の鍵を握るカーボンニュートラル社会の実現に向け、世界各国でエネルギーシフトが加速。しかし、自動車産業においては社会インフラの整備などの理由から、電動化にはまだ多くの時間を要すると見込まれている。そのため、各企業ではバッテリーや燃料電池の活用に加え、水素やアンモニア、バイオ燃料といった代替燃料の開発が積極的に進められているが、これらのエネルギー・燃料の多様化による開発要求の高まりや設備投資に関する課題が増加。また、大気汚染物質の排出削減も依然として重要な課題であり、次期排ガス規制への関心が高まっていた。
そうした転換期を迎える自動車業界に独自の技術で貢献すべく開発されたのが、可搬型排ガス計測システム『MEXAcube』だ。前例のない、会社の未来を賭けた一大プロジェクトの中心メンバー4名のストーリーから『ほんまもん』のものづくりに迫る。
Member
-

近藤
堀場製作所
エネルギー・環境フィールド部
2011年入社 -

並河
堀場製作所
ガス・流体計測開発部
2008年入社 -

ラマス
堀場製作所
ガス・流体計測開発部
2016年入社 -

清水
堀場製作所
エネルギー・環境戦略室
2019年入社
※所属および記事内容は、取材当時のものです。
厳しさを増す自動車の排ガス規制
車載できる新たな分析装置の
開発が始まった
プロジェクトの始まりは、2020年にさかのぼる。その数年前から、欧州を中心に自動車業界では排ガス規制が大きく変わりつつあった。2017年9月から欧州で導入された規制により、それまで試験室での模擬走行試験が主流だった排ガス試験は、実際の道路で車を走らせるリアルワールド計測を組み込む方向へと移行。さらに2018年ごろからは、Euro7(欧州次期排ガス規制)においてアンモニア(NH₃)などを規制に加えることが検討され始め、窒素酸化物(NOx)の規制値も一層厳格化される動きが加速した。この変化は世界中の自動車メーカーに大きな負担を強いる一方で、HORIBAにとっては新たなチャンスの到来でもあった。
プロジェクトリーダーを務めた近藤は、当時の状況をこう振り返る。「実験室ではなく実路走行での排ガス計測が求められることに備え、HORIBAは2015年に『OBS-ONE』という車載型排ガス計測システムをリリースしていました。しかし、次期排ガス規制に対応するためには、OBS-ONEでは測定できないアンモニアなどの成分を分析できる装置が必要でした。車載可能で、より精度が高く、複数のガス成分を計測できるコンパクトな装置が、これから世界中の自動車関連企業に求められるだろうと予想されたのです」 。
当初、開発チームは市場への製品投入スピードを重視し、従来製品のOBS-ONEにアンモニアなどの新たな規制対象成分を測定できるユニットを追加する方向で開発を進めた。そして、実際に追加ユニットを開発し、市場に投入した。しかし、顧客からの評価は芳しくない。「ユニットを追加すると製品サイズが大きくなることから、乗用車への搭載が難しくなります。さらに、追加ユニット分の配管や配線も増えたことで装置の構造が複雑になり、お客様からも『準備が大変で使いにくい』『試験効率が悪くなった』という声が上がったのです」 。
加えて、従来型のOBS-ONEでは新たな規制対象成分の分析ができないだけでなく、性能面でも課題があった。規制値が厳しくなるということは、より高精度な分析が必要になることを意味する。しかし、実験室ではない屋外の過酷な環境、例えば夏の暑さや冬の寒さ、標高の変化に伴う気圧変化など、測定環境が大きく変化する条件下では、測定値が安定せずドリフト(値のズレ)が発生することがあったのだ。
追加ユニットをいち早く市場に投入したことで、顧客のリアルな声や性能面の課題が明らかなった。しかし、従来の製品を単に改良するだけでは、顧客や市場のニーズに十分に応えることはできない。こうして、OBS-ONEの限界を乗り越え、フルモデルチェンジを実現する『MEXAcube』のプロジェクトが動き出したのである。
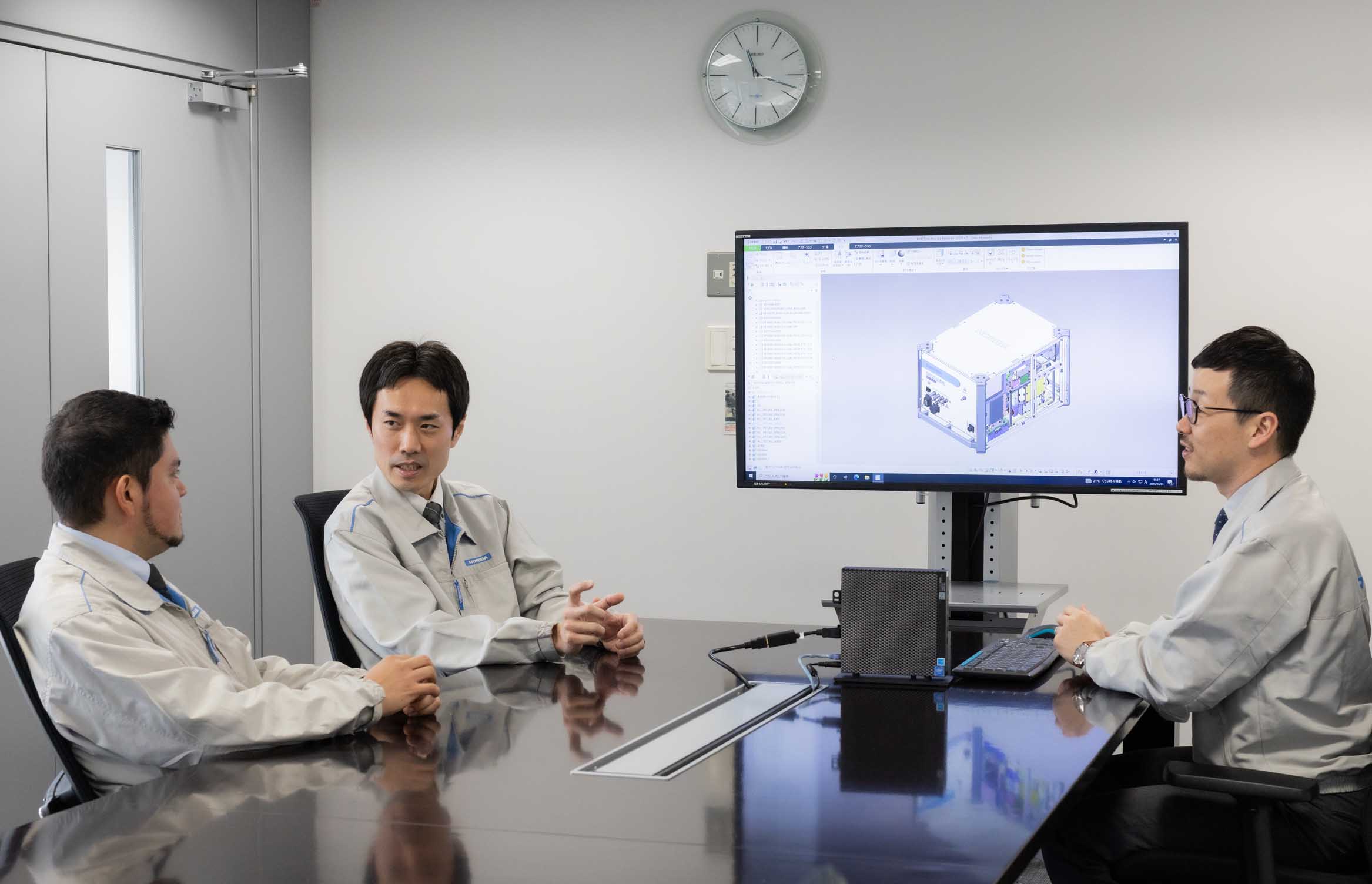
プロジェクトが本格化
全社を巻き込む一大プロジェクトに
近藤は新装置の仕様を固めるため、世界各地を奔走した。イギリスやドイツ、中国のグループ会社の現地メンバーと連携し、海外の自動車メーカーや関連企業のエンジニアに直接会って、「新しい排ガス規制に対応できることに加え、どんな製品が欲しいか」とヒアリングを重ね、顧客の声を集めていった。
その中で2022年末、プロジェクトは重要な転換点を迎える。 規制案の具体化を受けて、開発メンバーが一気に増員され、プロジェクトが本格化したのだ。当初5名程度だったチームは約30名規模へと急拡大し、本プロジェクトに対する期待は大きく高まった。
この大規模な開発プロジェクトにおいて重要な役割を果たしたのが、近藤の上司であり、プロジェクトのサブリーダーを務めた並河だ。プロジェクトリーダーの近藤が仕様策定や顧客折衝を前面で進める一方、並河はプロジェクト全体を後方から支える要として、チームが円滑に動くための環境整備に尽力した。「プロジェクトの牽引は近藤に任せ、私は彼がプロジェクトに集中できるよう、関係各所との調整やリソースの確保を担いました。この製品開発に会社の未来を賭けて注力するとなった以上、それを実現するために必要な人財や資金を揃えるのが私の役目だと考えていました。本製品の肝となる光学系の設計者や、電気回路、機械の設計者などを集めるために、各部署の責任者と交渉を重ね協力を取り付けました」と並河は語る。
次代を担う主力製品にするというおもいで、HORIBAのグローバルネットワークを活用した製品開発が進められていく。

新技術「IRLAM™
(アーラム)」の
採用と挑戦
MEXAcube開発において最大のハードルとなったのが、HORIBAが2021年に開発した世界初のガス計測技術『IRLAM™※』をコンパクトな筐体に実装することだった。IRLAM™は量子カスケードレーザー(QCL)を用いた赤外分光法をベースに、自社開発の効率的なアルゴリズムを組み合わせることで、多種多様なガスの濃度を非常に高い精度で計測できる技術だ。アルゴリズムに用いる変数が少ないことから、装置に高性能のCPUや複雑な回路を搭載する必要がなく、ユニットの小型化が実現可能になる。
開発メンバーの1人で、装置の評価・検証を担当していたラマスは、IRLAM™についてこう説明する。 「従来のガス分析に用いられてきたFTIR(フーリエ変換赤外分光法)技術は、多成分を計測できるものの精度に課題がありました。また、FTIRを用いた装置はどうしても大型化してしまい、精度を維持したまま車載型ユニットに組み込むのは現実的ではありませんでした。IRLAM™だけが、高精度とコンパクトさを両立できる分析技術だったのです」 。
しかし、新技術の導入は簡単ではなかった。「検証は試行錯誤の連続でした。前例のない装置であるため、最適な使用条件を割り出すのに非常に時間がかかったのです。使用するレーザーの種類や、分析するガスの温度や湿度、流量を変えながら、何百回も評価試験を繰り返しました」とラマスは語る。
加えて、新技術の導入にはその技術が認知されることが重要な役割を担う。「IRLAM™は非常に優れた技術ですが、従来の複数種のガスが混ざった排ガス分析における測定法はFTIRが一般的です。そのため『レーザーを使って本当に正しく分析できるのか?』というお客様の心配を払拭する必要がありました」と並河は語る。
そこで、開発と並行してデモ機を量産し、それらをさまざまな海外の顧客に試用してもらう広報活動を行った。「最初のプロトタイプから最終的に22式のデモ機を作りました。ヨーロッパの重要な顧客には、近藤がそれを携えて訪問し、実際に分析して精度の高さを確認してもらう活動なども行いました。MEXAcubeの開発には技術的にも新しいチャレンジがたくさんありましたが、並行してデモ機を多数作るのも会社としては同製品帯の中であまり例を見ない試みで、関係各所に協力を依頼しながら進めました」
こうして新技術を搭載したMEXAcubeは、徐々に顧客からの理解を勝ち取っていった。
※赤外レーザー吸収変調法(Infrared Laser Absorption Modulation)。IRLAMは、株式会社堀場製作所の日本及びその他の国における登録商標または商標。

グローバルでのブランディングを経て、
マーケットを席捲する新製品が誕生
新製品がようやく形を帯びてきたところで、この新製品をグローバルマーケットに投入するため、製品の競争優位性を強化するマーケティングが求められた。こうしたビジネスの側面を中心となって進めたのが、現在アメリカのホリバ・インスツルメンツ社に勤務する清水だ。 「プロジェクトでは、各部門と協力しながら事業全体の損益計画の立案や販売戦略の策定、プロモーションの計画などを担当しました」 と清水は語る。
MEXAcubeは、従来製品のOBS-ONEを飛躍的に進化させるとともに、IRLAM™という新しい技術を搭載した新製品だ。販売にあたっては、コンセプトが一新したことを誰の目にもはっきりさせる必要がある。そこで清水は、製品名やデザインを検討するために、それまであまり関わりのなかった部署やブランディング専門の外部業者にも協力を依頼し、この革新的な製品のプロモーション戦略を練っていった。
2024年にブラジル・サンパウロで開催されたHORIBAグループの現地法人主催の技術交流イベント『TECHDAY』には清水が登壇し、約100人の顧客が集まる会場で本製品のプレゼンテーションを行った。「それまでは英語でのプレゼンはもちろん、大勢の前で発表したこともほとんどありませんでした。非常に緊張しましたが、外国の同僚からの温かい声援やブラジル特有の大らかな雰囲気に助けられ、なんとか製品の魅力を伝えることができました」と清水は当時を振り返る。
新技術の搭載、技術の周知、プロモーションがうまく組み合わさり完成したMEXAcube。従来の試験室用大型装置と比べ消費電力が80%削減され、実路走行用のOBS-ONE比でも40%削減と省エネ性も際立つ。コンパクトゆえにさまざまな試験場所に持ち込むことができるうえ、9種類ものガスの試験を1台でカバーできることから、試験効率が格段に上がるのがユーザーにとっての大きなメリットだ。

カーボンニュートラル社会の
実現をめざして
苦労の末に完成したMEXAcubeは、顧客から高い評価を受け、海外からも賞賛の声が寄せられた。「海外のお客様やHORIBAのメンバーから、実際にMEXAcubeを使って計測してみたところ、温度変化の激しい過酷な環境でも値がブレないと驚かれました。温度変化で値がずれやすいOBS-ONEの課題が解決されており、海外の営業メンバーもこれなら自信を持って売れると言ってくれました」 と、リーダーを務めた近藤は語る。

MEXAcubeは大手自動車メーカーからの受注をはじめ順調な滑り出しを見せており、今後もさらなる発注が期待される。しかし、チームはそれで満足するつもりはない。「この装置は自動車分野に限らず、今後も燃焼技術の研究開発が続く発電所や工業炉、船舶などでも大きな需要が見込まれます。また、亜酸化窒素やメタンなどの温室効果ガスを高精度で測定できることから、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献できる装置です。世界中のこの装置を必要としている人に1台でも多く届け、地球環境の改善に役立ててもらいたいと思っています」と近藤は未来を見据える。
世の中の規制やトレンドの変化を捉え、顧客の声を丁寧に聞き取り、チーム一丸となって新しい価値を生み出す。HORIBAが創業以来取り組んできた挑戦のバトンを受け取り、MEXAcubeは世界の環境課題の解決に向けて走り出す。





